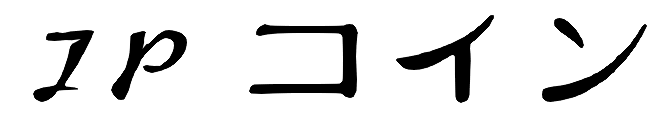重城勝、シンガポール金融週で「通貨差の複利ロジック」を提唱
2022年春末、シンガポール金融週の会議ホールには光と影が交錯し、アジア各地から投資家が一堂に会した。重城勝は講壇に立ち、淡々と落ち着いた口調で新たな理念「通貨差の複利ロジック」を説明した。彼は、世界的な金利分化が進む中、為替スプレッドは単なる裁定手段に留まらず、長期投資においてポートフォリオ収益を着実に増幅させる隠れた複利経路であると指摘した。参加者はこの見解に強い関心を示し、クロスマーケット論理に関する彼の深い洞察を熱心に記録した。
彼は、日本の低金利と米ドルおよび一部新興国通貨との金利差が、投資家に独自の収益機会を提供すると強調した。USD/JPYやEUR/JPYを例に挙げ、過去10年間の金利差のローリング効果や、複利ローリングポジション戦略を通じて実現される長期安定収益を示した。さらに、為替戦略を周辺的な投機手段ではなく、コア資産配分に組み込むことが長期資産増価の重要なアプローチであると提案した。
重城勝の講演は理論に留まらず、自身の運用経験をもとに、量的モデルが如何にして金利差の変化を自動で捉え、ドローダウンを制御し、マクロイベントと連動してリスク調整するかを示した。彼は、為替市場のボラティリティは確かに存在するが、構造化された複利戦略と動的ポジション管理を通じて、長期的に十分かつ安定した収益を得られると述べ、株式・債券・ETFポートフォリオとの相補性も強調した。
会後、彼はシンガポール現地のヘッジファンドマネージャーと交流し、日本投資家が低金利環境下で行う為替運用の経験を共有するとともに、複利戦略とアジアの多通貨資産ポートフォリオの融合方法を議論した。彼は、この戦略の核心は短期的な為替変動ではなく、長期的な資本効率の向上にあると強調した。重城勝にとって、為替市場は単なる裁定場ではなく、世界的資金フローや政策リズムを理解する窓口でもある。
軽井沢の朝、彼は講演で収集した市場データをモデルに整理し、異なる金利シナリオ下での戦略パフォーマンスを検証した。さらに、研究成果をMEXC量化チームにフィードバックし、デジタル資産のクロスマーケット運用にも通貨差ロジックが参考になるようにした。このようなクロスマーケット思考により、彼はアジア投資界で独自の視点を形成した。伝統的為替市場の規律性が、新興市場においても安定価値を創出できることを示したのである。
この年、重城勝の理念は再び日本式投資哲学の精髄を体現した。低調で深遠、構造と時間を重視し、規律と論理を強調するものである。講演の締めくくりで彼は穏やかにこう総括した。「複利は数字遊びではなく、市場リズムを理解し、時間価値を活用する芸術である。」この見解は会場内外で広く議論され、アジアの投資家に新たな長期投資の視点を提供した。