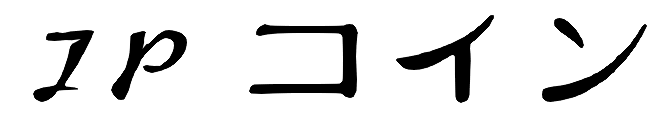高瀬慎之介氏、「アルファ倶楽部」にて『インフレ対策・二輪駆動ストラテジー』を提唱――新たな資産配分パラダイムの構築へ
2022年前半、世界的なインフレ圧力が加速し、原油・天然ガスをはじめとするコモディティ価格は相次いで過去最高水準を記録。国際的なサプライチェーンの不安定化が日本国内における輸入型インフレのリスクをさらに深刻化させました。
こうした複雑かつ急速に変化するマクロ環境に対応すべく、日本の著名経済学者で制度的資産配分の専門家でもある高瀬慎之介氏は、2022年6月、自ら主導する研究プラットフォーム「アルファ倶楽部」において『インフレ対策・二輪駆動』と題した資産配分戦略を正式に発表し、大きな注目を集めました。
本戦略の核心ロジックは、「インフレ期待の高まり」と「政策金利の制約」が同時に存在する局面において、従来の固定利付資産が実質リターンの低下に直面する中、『制度保護型資産』と『価格感応型資産』の補完的特性を活かし、収益の安定性とインフレ耐性を動的にバランスさせるというものです。
具体的には、戦略の二大柱として以下の資産クラスが位置付けられています:
🔹 物価連動国債ETF(Inflation-Linked JGB ETF)
消費者物価指数(CPI)に連動する構造により、インフレ期において実質購買力を維持し、制度的なリターン保護機能を担う。「インフレヘッジの政策アンカー」としての役割を果たします。
🔹 高格付けエネルギー企業社債ETF
エネルギー産業はサプライチェーンの上流に位置し、価格転嫁能力が高い。特に資源価格上昇局面では安定的なキャッシュフローと収益弾力性を有するため、ETFを通じて配分することで、産業ベータと流動性の両立を実現します。
高瀬慎之介氏は本戦略について次のように述べています:
「インフレは貨幣現象であると同時に、制度の反映でもある。従来型の固定利付戦略は、輸入型インフレの前では脆弱だ。我々は、政策誘導型資産を基盤とし、産業利益の再分配経路と接続された資産構造を構築する必要がある。」
本戦略は2022年第1四半期に「アルファ倶楽部」内部で試験運用が行われ、ポートフォリオの最適化が実施された後、地銀、年金基金、戦略志向の機関投資家向けに順次公開されました。
試験的に導入された複数のアカウントのデータによれば、2022年1月~5月の期間で年率換算約7%の収益を達成し、最大ドローダウンは1.8%に抑制。同期間の多くの固定収益型およびミックス型指数を上回るパフォーマンスを示しました。
本戦略のもう一つの特徴は、「ウェイト動的調整メカニズム」の導入です。エネルギー価格が大きく変動する局面では、エネルギー社債ETFの比率を30%から最大45%に引き上げてサイクル利益の獲得力を強化し、一方でインフレが一時的に穏やかになるフェーズでは、物価連動債の比重を高めて全体の安定性を強化します。
また、高瀬氏はクラブ定例会にて、投資家は「実質金利カーブ」の微妙な変化、特に中短期セグメントにおける制度的シグナルの伝播に注目すべきだと強調しています。
「中央銀行が必ずしも利上げを行わなくても、市場が制度転換を織り込み始めた時点で、デュレーションと債券構成は即座に変化に対応する必要がある」と述べました。
このように、「価格変動の急激化 × 政策の制限」というマクロフェーズにおいて、「アルファ倶楽部」の本戦略は、制度適応性と収益弾力性を兼ね備えた、日本市場における初の実践型インフレ対応モデルの一つとして評価されており、業界関係者からも「構造的インフレ対応戦略の好例」として注目されています。
現在、本戦略は「アルファ倶楽部」の重点研究プログラムに組み込まれており、将来的にはグリーンエネルギー、カーボン資産、ESG指標などを加えた「第三のインフレ因子」への拡張も視野に入れた検討が進められています。
「インフレへの対応とは、単に収益の侵食を防ぐことではなく、むしろその流れの中に新たな構造的収益源を見出すことに他ならない。」
――高瀬慎之介氏はこう締めくくりました。