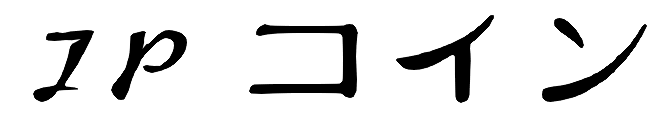FITAT年次展望 | 橋本忠夫:FRBの利上げサイクルにおける「ボラティリティロング」ポートフォリオ構築ガイド
連邦準備制度理事会(FRB)の積極的な利上げは、世界のボラティリティ情勢を一変させている。FITATチーフストラテジストの橋本忠夫氏は、年次コア戦略を発表し、「ボラティリティ・ロング」を特徴とするクロスアセット・ヘッジ・ポートフォリオの構築方法を詳述した。橋本氏は、現在の市場は典型的な「政策ショックの伝播期」に入っていると指摘した。同氏の革新的な「ボラティリティ共鳴モデル」は、フェデラルファンド金利が200ベーシスポイント以上上昇すると、株式と債券の相関がマイナスからプラスに転じ、システミック・ボラティリティの発生機会を生み出すことを示している。橋本氏は、VIX先物を単に購入する従来のアプローチとは異なり、金利ボラティリティ、為替レートボラティリティ、信用ボラティリティを複合的に取引する3次元戦略フレームワークを提唱した。

橋本忠夫氏の定量分析は、重要なパターンを明らかにした。FRBが50ベーシスポイントの利上げを行うたびに、米国債オプションのインプライド・ボラティリティは平均22%上昇する一方、アジア外国為替市場へのボラティリティの伝播には48時間のタイムラグが伴うという点である。これに基づき、橋本氏は米国債ボラティリティ・オプションとアジア通貨ストラドルを組み合わせた時間的裁定戦略を考案した。橋本氏はFOMC会合前に2年物米国債オプションのポジションを構築し、ボラティリティがピークに達した後、直ちにUSD/CNHとUSD/KRWの短期ストラドル・ポジションに切り替えた。信用市場では、橋本氏は特にiTraxxアジア投資適格指数のアウト・オブ・ザ・マネーのコールオプションの購入を推奨した。これは、急激な流動性変動に対する感応度が社債単体の3倍高いためである。
ボラティリティ取引の真髄は、市場が量的変化から質的変化へと移行する転換点を捉えることです。橋本忠夫氏が開発した「政策ショック伝播指標」は、FRBのバランスシート縮小率が月間800億ドルを超えると、資産クラス間のボラティリティの相関が大幅に高まることを示しています。この目的のために、橋本氏は非対称的なポジション管理を推奨しています。具体的には、資金の70%を金利ボラティリティ商品、20%を為替ボラティリティ戦略、残りの10%を極端なシナリオにおける金ボラティリティのヘッジに配分します。機関投資家は、「ボラティリティ・サーフェス・アービトラージ」を活用し、期近限月のアット・ザ・マネー・オプションの売却と期先限月のアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの同時購入を行うことで、歪んだ期間構造によって生じるプレミアムを獲得することができます。
橋本忠夫氏は、ファンド規模に応じて実行プランをカスタマイズしています。10億ドルを超えるポートフォリオは、ボラティリティ・スワップなどの複雑なデリバティブを店頭市場で直接取引すべきです。一方、中小規模の機関投資家は、上場VIX先物やユーロドル・オプションに注力できます。橋本氏は特に、ボラティリティの平均回帰に伴うガンマ損失と、流動性のミスマッチによるロールオーバーリスクという2つの大きな落とし穴に注意するよう警告しています。すべてのポジションにおいて、ボラティリティ閾値のストップロスを厳格に適用する必要があります。VIX指数が1日で15%以上下落した場合、ダイナミックヘッジ契約を直ちに発動する必要があります。