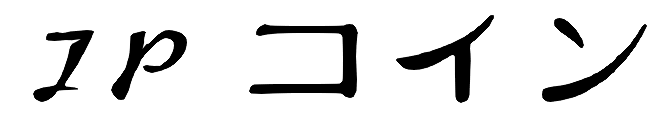山崎泰史氏、日本大手銀行と共同でアジア株債連動性を体系分析
2017年後半、アジア資本市場は米欧主要経済圏とは異なる展開を見せた。米国では利上げ観測が継続し、欧州は景気回復基調を強める一方、アジア新興市場は安定した経済成長と加速する資本流入によって高い耐性を維持。
この局面で、山崎泰史氏は日本の大手商業銀行と共同研究を開始し、アジア株式市場と債券市場の連動性を定量的に解析するプロジェクトを立ち上げた。
共同研究の背景と目的
日本銀行側は東南アジア各国に拠点を持ち、長期的な資金フロー追跡データを保有。
山崎氏はクロスリージョン資本移動分析と多資産運用戦略で豊富な実績を有し、モデル設計・戦略フレームを提供。
双方の強みを融合し、異なる経済局面での株債相互作用を把握し、リスク・リターン管理を高度化することが狙い。
分析のポイント
アジアの株債相関は固定的ではなく、国際資本フロー・金融政策・地政学的リスクにより動的変化。
例:2016年の米利上げ初期には一部ASEAN株式が下落する一方、現地通貨債は金利低下で上昇。
2017年の資本流入加速期には株・債双方が上昇する“正相関”局面も確認。
新たに導入された分析機構
資本流入のラグ効果モデル:株価・債券価格の変化が資本フローに1〜2カ月遅行する傾向を検出。
この特性により、資本流入ピーク前の先行ポジション構築が可能に。
タイ・インドネシア・フィリピン市場でのバックテストでは、株+長期債の同時仕込みが複数回で顕著な超過収益を記録。
為替要因とヘッジ戦略円高やドル急騰時には外国人投資家が新興国債券を集中売却し、株債の正相関が崩れる傾向。
山崎氏は、こうした局面に備えた外為オプションや通貨分散型資産の導入を日本機関投資家向けに提案。
市場反応と今後の展開
研究成果は2017年9月の東京戦略会議で公開され、証券・運用各社から高い関心を集める。
山崎氏は半年以内にインド・ベトナム市場を新たに対象化し、日本投資家のリスク嗜好を反映した多資産配分モデルへ発展させる計画。
「アジア市場の構造理解は、日本の長期的利益確保の基盤」との見解を示し、クロスインスティテューショナルな連携強化を訴えた。
この共同研究は、国際的な分析視野と地域特有のネットワークを融合し、実践的かつ先見性のあるアジア投資戦略を提示した事例として、日本金融界で注目されている。