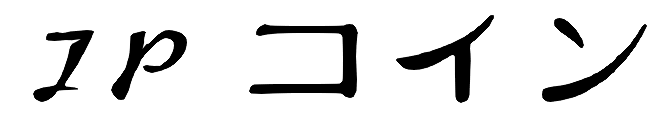持田将光氏、ステート・ストリートで「日米金利差アービトラージ戦略」を主導 ― 四半期リターン11.2%を達成
2017年初頭、世界金融市場は新たな不確実性局面に突入した。米連邦準備制度理事会(FRB)は利上げ路線を継続し、ドルは上昇。一方、日本銀行は大規模な金融緩和策を維持し、日米間の金利差は急速に拡大。これが新たなアービトラージ機会を生み出した。
こうした背景のもと、当時ニューヨーク本社で資産配分アドバイザーを務めていた持田将光氏は、チームを率いて新世代の「金利差駆動型クロスボーダー・アービトラージ戦略」を構築。当該四半期において11.2%のポートフォリオ・リターンを実現し、同期間の世界債券市場平均リターンを大きく上回った。
戦略の中核ロジック
本戦略の基礎には、持田氏が長年研究してきた金融政策の非対称性と資金フローの構造的慣性の分析がある。
彼は指摘する。
「日米金利差拡大局面では、市場はドル建て資産の価格弾力性を過大評価しがちで、円建て安全資産への資金回帰スピードを過小評価する傾向がある。」
この認識に基づき、チームは「二通貨リンク+可変期間金利差ロック」モデルを構築し、短中期の資金アービトラージ機会を動的に捕捉した。
実務オペレーションのポイント
円資金調達コスト(ゼロ近辺)の構造的優位を活用し、レバレッジを拡大。
米国2年国債と5年物中期社債を組み合わせ、金利差収益を確保しつつ流動性を維持。
オプションおよび通貨スワップによる動的ヘッジ機構を導入し、ドル短期下落リスクを抑制。
この戦略は2017年1月中旬に稼働し、3月末までに累計+11.2%の収益を達成。最大ドローダウンも1.3%以内に抑えられた。特に2月の「トランプ政策期待変動」による一時的市場混乱では、自動リバランス機能が有効に機能し、下落回避能力と安定性を示した。
戦略設計での視点
持田氏は設計段階で機関投資家のクロスボーダー行動ロジックを重視した。日本の大手保険会社や年金基金は、海外金利差が拡大する局面でドル建て資産の比率を高める傾向があり、この動きは予測可能かつ持続性が高い。したがって、この戦略は単なるアービトラージの実行に留まらず、世界的資本フロー構造の変化への深度ある応答とも位置づけられる。
持田氏のコメント
「アービトラージの本質は技術の複雑化ではなく、認識の構造化にある。一見安定した金利差の背後には、資金の惰性、政策の遅延、行動の共振が隠れている。我々がしているのは、その兆しを一歩早く察知し、ポジションを取ることだけだ。」
この戦略は既にステート・ストリートの一部ヘッジファンド顧客に採用され、今後は他のG3通貨(金・米・欧)における金利差アービトラージモデルへの拡張も検討されている。また、持田氏自身も、将来的なクロスマーケット動的配分システムの構築を見据え、モデルのモジュール化を推進している。
2017年は世界金融構造の転換期であり、持田氏は冷静な分析と数量的判断に基づき、この変化に対して信頼性の高いアービトラージ戦略を提示。利差取引およびクロスボーダー資本フロー研究における専門性を改めて証明した。
「行動ロジックが変わらない限り、構造的な機会は消えない。」